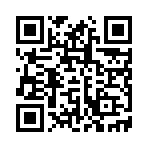スポンサーリンク
トンネル内の橋
やっとぶーさんのお返事を書く準備ができました。本当に遅くなりました。
まず、もし新聞に出ていたのならこんな写真ではなかったでしょうか?

TBMで掘った断面は円形をしています。
飛騨トンネルでは、下半分をトンネル内の換気用に使用し、
その上に路面を造る計画ですので多少複雑な構造になります。
そこで下半分を造りながら、トンネルを掘削するための材料の搬入ルートを
確保する方法がトンネルの中に橋を掛ける工法でした。
上の写真はトンネルの下半分を撮影したものです。
作業用の橋の下側とアーチ状のコンクリートの部品が見えています。
アーチ状のコンクリートは作業用の橋から吊り下ろされ設置されます。
アーチ状コンクリートの下側が、トンネル換気のための風の道になります。
このアーチの上に土を持って路面を造ります。
路面側から撮った写真が下の写真です。

手前が、土が盛られた部分で、この奥でトンネルの掘削がなされています。
真ん中の通路から先が作業用の橋になっています。
今は、全ての掘削作業が終了したのでこの橋は、解体されています。
まず、もし新聞に出ていたのならこんな写真ではなかったでしょうか?

TBMで掘った断面は円形をしています。
飛騨トンネルでは、下半分をトンネル内の換気用に使用し、
その上に路面を造る計画ですので多少複雑な構造になります。
そこで下半分を造りながら、トンネルを掘削するための材料の搬入ルートを
確保する方法がトンネルの中に橋を掛ける工法でした。
上の写真はトンネルの下半分を撮影したものです。
作業用の橋の下側とアーチ状のコンクリートの部品が見えています。
アーチ状のコンクリートは作業用の橋から吊り下ろされ設置されます。
アーチ状コンクリートの下側が、トンネル換気のための風の道になります。
このアーチの上に土を持って路面を造ります。
路面側から撮った写真が下の写真です。

手前が、土が盛られた部分で、この奥でトンネルの掘削がなされています。
真ん中の通路から先が作業用の橋になっています。
今は、全ての掘削作業が終了したのでこの橋は、解体されています。
Posted by NEXCO@kiyomi at
◆2008年01月16日11:58
│お返事
かわずぅさんへのお返事
かわずぅさんがご覧になったいら谷トンネルも今はもうこんな感じです。飛騨トンネルと大牧トンネルを除く8本のトンネルはもういつでも開通できる状態です。入り口には情報板が立っていて標識も設置完了しています。

トンネル内には照明、消火栓が既に設置されていて、最終の試験調整待ちです。(写真は舟原トンネル)


トンネル内には照明、消火栓が既に設置されていて、最終の試験調整待ちです。(写真は舟原トンネル)

Posted by NEXCO@kiyomi at
◆2007年12月28日09:05
│お返事
気合の入ったお答え
やどっち4号様
すみません。土木の技術者の渾身の回答には、写真が入りましたのでこちらで答えさせていただきます。また、ご質問の砂圧は土圧に直させていただきました。
大きな土圧がかかった箇所における土圧対策について
昔のトンネルを掘る時、掘っていたトンネルが、崩落した後をみるとアーチ状に崩落してそれ以上崩れないことを発見し、現在のトンネルの形となっています。
このアーチ状となったトンネルは,崩れづらく,自らを支える力を持っているので潰れません。
現在掘られているNATMは,このようにトンネル周囲の地山が,トンネル自らを支えるという支保機能を利用した掘削技術です。
しかし,表面から亀裂や湧水が発生したり,地質にムラがあると,支えきれず崩壊してしまいます。このため工事では,表面を吹付けコンクリートで固め,ロックボルトを打ち込み,より深いところまでトンネルを一体化させます。さらに地山の安定度に応じて,トンネルの外周に沿って鋼製の型枠(支保工)などを取り付けトンネルを掘ります。
「「NATM」は New Austrian Tunneling Method の頭文字を取ったもので、「ナトム」といいます。」しかし、こうした対策を行ってもそれ以上の土圧がかかった場合には鋼製の支保が耐えられず曲がったり、コンクリートにヒビが入ったり、トンネルの内側に収縮したりとます。
これらの対応として、飛騨トンネルでは鋼製の支保のピッチを縮めたり、インバートコンクリートを打ち込み、出来るだけ円形に近い形にすることで強大な土圧に対抗ししていきます。
また、トンネルの中が設計より収縮した場合には設計の大きさに再度内側から掘ることもしてます。
この時点でトンネルの収縮がなくなったことを確認することでトンネルが自ら支えることが出来たことになりトンネルは安定します。
トンネルはこれで安定し大丈夫ですが、トンネル内の走行製の確保、地震時対策、トンネル内の火災等に対応するため、その後内側にコンクリートを約30cm~40cm巻ことによってみなさまが安心して通行出来るように作ってます。飛騨トンネルは、しっかり対策をしましたので安心して通行してください。
用語の図示

土圧がかかっだ場合の変形写真(盤膨れ)

すみません。土木の技術者の渾身の回答には、写真が入りましたのでこちらで答えさせていただきます。また、ご質問の砂圧は土圧に直させていただきました。
大きな土圧がかかった箇所における土圧対策について
昔のトンネルを掘る時、掘っていたトンネルが、崩落した後をみるとアーチ状に崩落してそれ以上崩れないことを発見し、現在のトンネルの形となっています。
このアーチ状となったトンネルは,崩れづらく,自らを支える力を持っているので潰れません。
現在掘られているNATMは,このようにトンネル周囲の地山が,トンネル自らを支えるという支保機能を利用した掘削技術です。
しかし,表面から亀裂や湧水が発生したり,地質にムラがあると,支えきれず崩壊してしまいます。このため工事では,表面を吹付けコンクリートで固め,ロックボルトを打ち込み,より深いところまでトンネルを一体化させます。さらに地山の安定度に応じて,トンネルの外周に沿って鋼製の型枠(支保工)などを取り付けトンネルを掘ります。
「「NATM」は New Austrian Tunneling Method の頭文字を取ったもので、「ナトム」といいます。」しかし、こうした対策を行ってもそれ以上の土圧がかかった場合には鋼製の支保が耐えられず曲がったり、コンクリートにヒビが入ったり、トンネルの内側に収縮したりとます。
これらの対応として、飛騨トンネルでは鋼製の支保のピッチを縮めたり、インバートコンクリートを打ち込み、出来るだけ円形に近い形にすることで強大な土圧に対抗ししていきます。
また、トンネルの中が設計より収縮した場合には設計の大きさに再度内側から掘ることもしてます。
この時点でトンネルの収縮がなくなったことを確認することでトンネルが自ら支えることが出来たことになりトンネルは安定します。
トンネルはこれで安定し大丈夫ですが、トンネル内の走行製の確保、地震時対策、トンネル内の火災等に対応するため、その後内側にコンクリートを約30cm~40cm巻ことによってみなさまが安心して通行出来るように作ってます。飛騨トンネルは、しっかり対策をしましたので安心して通行してください。
用語の図示

土圧がかかっだ場合の変形写真(盤膨れ)
Posted by NEXCO@kiyomi at
◆2007年12月27日21:32
│お返事